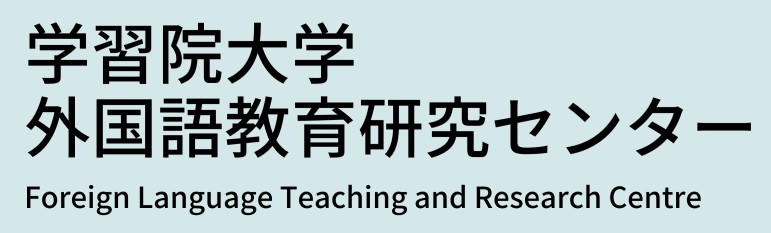所長ご挨拶
そうだ 外国語、学ぼう。 堀内 ゆかり
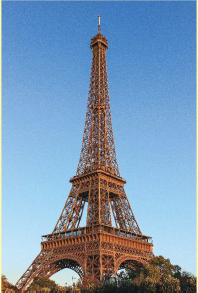
春は新しいことを始めたくなる季節です。 新入生のみなさんも、 2年以上のみなさんも、 新しい言葉を学び始めてみませんか?どの言語にするかは思いつき、 直感に従ってピンときたものを選びましょう。 外国語教育研究センターでは英語、 ドイツ語、 フランス語、 中国語、 スペイン語、 イタリア語、 ロシア語、 アラビア語、 韓国語と、 留学生向けの日本語の授業を提供しています。大学では、 所属する学部・学科の履修規定に従って卒業に必要な単位を取得していきますが、 その一方で、 学費は定額で学び放題の 「サブスク 」 です。 時間割を組む時に空きコマがあったら外国語を入れてみる、 というような気軽なきっかけでかまいません。
Google翻訳などの自動翻訳や、 自動翻訳機が急速に発達し実用化している今、 外国語のどんな能力が必要でしょうか?想像してみてください。 たとえば、 どこか外国に行って、 初対面の相手に自分の言いたいことを伝えたいとき、 いきなりスマホの自動翻訳を使ったら?― 相手は不快に感じるはずです。 自動翻訳を使う前に、 相手との信頼関係が築かれていることが重要です。
ここでの信頼関係とは別にむずかしいことではなく 、 まずは挨拶。 英語圏以外の国では、 現地の言葉で挨拶したほうが望ましいです。 それは日本で、外国人に 「Hi」 「Thank you」 と言われるより 「コンニチハ」 「アリガト 」 のほうが嬉しいのと同じです。 他に 「おいしい! 」 や、 1 、 2 、 3の簡単な数字を覚えて、 機会があったら旅行に行って実際に使ってみてください。 英語学習の場合は、 アジアなど英語圏以外の国で使ってみるのがおすすめです。
最初のハー ドルは低く設定して、 楽しく学習しましょう。 三日坊主でも、 独学でも、 興味が湧いてから授業を受講するのもありです。 外国語学習は単なる意思疎通に役立つだけでなく 、 自らと他者の違いを自覚する手段でもあり、他の文化をより深く理解する一助となります。
PASSPORT Vol.27より